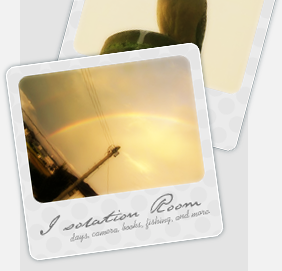- ハスラー来る (06/26)
- 第9回 マテガイ (06/24)
- 第8回 ナミマガシワ (06/21)
- 微小貝天国へ (06/18)
- 黒いヤツら (06/17)
- まさかの出会い (06/16)
- 第7回 ハツユキダカラ (06/14)
- 拾った猫、その後 (06/13)
- 自転車 (1)
- 日記 (474)
- ビーチコーミング (233)
- 小松海岸の貝図鑑 (11)
- リバーコーミング&陶片&ビン (65)
- 骨董 (3)
- 写真 (110)
- カメラ (52)
- ニュース (99)
- 家族 (48)
- 徳島ラーメン (127)
- アクアリウム (76)
- 神社仏閣 (48)
- 民俗学 (20)
- 釣り (70)
- ゴルフ (9)
- 料理 (22)
- 本 (39)
- ゲーム (46)
- 音楽 (15)
- 映画 (12)
- 宝石・天然石 (11)
- 陶芸 (1)
- シルバーアクセサリー (11)
- アイテム (13)
- バトン (28)
- 思考 (27)
- グルメ (5)
- その他 (97)
- インフォメーション (32)
- April 2025 (1)
- January 2025 (1)
- November 2024 (1)
- May 2024 (1)
- January 2023 (1)
- November 2022 (1)
- August 2022 (1)
- June 2022 (1)
- April 2022 (1)
- April 2021 (1)
- March 2021 (1)
- January 2021 (1)
- December 2020 (2)
- September 2020 (1)
- July 2020 (1)
- March 2020 (2)
- February 2020 (4)
- January 2020 (1)
- December 2019 (3)
- November 2019 (4)
- October 2019 (3)
- September 2019 (1)
- August 2019 (4)
- July 2019 (1)
- June 2019 (2)
- May 2019 (1)
- April 2019 (1)
- March 2019 (2)
- February 2019 (3)
- January 2019 (3)
- December 2018 (2)
- October 2018 (2)
- September 2018 (2)
- July 2018 (1)
- June 2018 (2)
- May 2018 (3)
- March 2018 (2)
- February 2018 (1)
- January 2018 (3)
- December 2017 (2)
- October 2017 (3)
- August 2017 (4)
- April 2017 (2)
- March 2017 (2)
- January 2017 (1)
- December 2016 (5)
- November 2016 (4)
- October 2016 (4)
- September 2016 (3)
- August 2016 (1)
- July 2016 (2)
- June 2016 (4)
- May 2016 (1)
- March 2016 (2)
- February 2016 (1)
- January 2016 (7)
- December 2015 (6)
- November 2015 (1)
- October 2015 (4)
- September 2015 (12)
- August 2015 (2)
- July 2015 (11)
- June 2015 (3)
- May 2015 (2)
- April 2015 (3)
- March 2015 (1)
- February 2015 (5)
- January 2015 (6)
- December 2014 (5)
- November 2014 (4)
- October 2014 (6)
- September 2014 (14)
- August 2014 (11)
- July 2014 (9)
- June 2014 (17)
- May 2014 (3)
- April 2014 (5)
- March 2014 (7)
- February 2014 (4)
- January 2014 (5)
- December 2013 (7)
- November 2013 (10)
- October 2013 (10)
- September 2013 (14)
- August 2013 (5)
- July 2013 (6)
- June 2013 (7)
- May 2013 (8)
- April 2013 (10)
- March 2013 (8)
- February 2013 (7)
- January 2013 (2)
- December 2012 (8)
- November 2012 (8)
- October 2012 (4)
- September 2012 (13)
- August 2012 (6)
- July 2012 (8)
- June 2012 (13)
- May 2012 (11)
- April 2012 (7)
- March 2012 (6)
- February 2012 (3)
- January 2012 (6)
- December 2011 (4)
- November 2011 (6)
- October 2011 (6)
- September 2011 (6)
- August 2011 (9)
- July 2011 (8)
- June 2011 (5)
- May 2011 (14)
- April 2011 (15)
- March 2011 (12)
- February 2011 (4)
- January 2011 (9)
- December 2010 (13)
- November 2010 (3)
- October 2010 (8)
- September 2010 (11)
- August 2010 (5)
- July 2010 (11)
- June 2010 (5)
- May 2010 (11)
- April 2010 (9)
- March 2010 (12)
- February 2010 (10)
- January 2010 (10)
- December 2009 (15)
- November 2009 (15)
- October 2009 (5)
- September 2009 (9)
- August 2009 (13)
- July 2009 (14)
- June 2009 (3)
- May 2009 (5)
- April 2009 (5)
- March 2009 (3)
- February 2009 (8)
- January 2009 (16)
- December 2008 (3)
- November 2008 (6)
- October 2008 (5)
- September 2008 (13)
- August 2008 (18)
- July 2008 (23)
- June 2008 (24)
- May 2008 (31)
- April 2008 (32)
- March 2008 (24)
- February 2008 (31)
- January 2008 (12)
- December 2007 (15)
- November 2007 (9)
- October 2007 (13)
- September 2007 (5)
- August 2007 (10)
- July 2007 (5)
- June 2007 (10)
- May 2007 (17)
- April 2007 (12)
- March 2007 (11)
- February 2007 (19)
- January 2007 (22)
- December 2006 (17)
- November 2006 (37)
- October 2006 (18)
- September 2006 (35)
- August 2006 (40)
- July 2006 (13)
- June 2006 (33)
- May 2006 (31)
- April 2006 (36)
- March 2006 (38)
- February 2006 (31)
- January 2006 (19)
- December 2005 (45)
- November 2005 (36)
- October 2005 (27)
- September 2005 (35)
- August 2005 (34)
- July 2005 (36)
- June 2005 (25)
- May 2005 (3)
- April 2005 (9)
- March 2005 (4)
- February 2005 (14)
- January 2005 (18)
- December 2004 (8)
- November 2004 (1)
- October 2004 (18)
- September 2004 (9)
2014.06.26 Thursday

6月21日、ハスラー納車しました。
思っていたより随分早い……しかし、それでも十分待たされた、という感じです。
まだ乗って数日ですが、ごく簡単なレビューを書いておきます。
1、外装・外観
ツートンの境目は綺麗に処理されています。
高さがあることで、なんだか寸詰まりに見えますw
タイヤハウスとタイヤの隙間が広いので、多少違和感があります。
2、内装・内観
予想通りチープです。
高級感は期待していなかったので別にいいんですけどね。
各所にある収納ですが、正直なところ使い勝手はイマイチ。
特にドリンクホルダーが使い辛いです。
ナビと連携するためのUSB端子が、かなり下の方にあるのもちょっと……。
まぁ、USB端子は延長コードを使えば、大きな問題はありません。
広さは思ったより余裕があるかな、といった感じ。
3、機能
オプションのHIDオートライトは地味に便利です。
スピードメーター下の液晶アニメーション(燃費、ガソリン残量、タコメーターなどなど)が表示されるディスプレイは、情報量的な意味では悪くないのですが、やはり別にタコメーターが欲しかったな、と思います。
趣味車、遊び車というなら尚更です。
時速30km以下で作動するという自動ブレーキ的なものは、今のところ必要な状況に出会っていないので何とも言えませんし、これからもないことを祈りますw
燃費はターボのわりに非常に良いと思います。
(俺のハスラーはGのCVT、FFターボです)
4、問題点
納車から数日ですが、早々にトラブルが発生。
雨漏りです。
ハスラーの雨漏りに関してはネット上でかなり前から有名でして、ウェザーストリップや板金精度の問題ではないか、と言われています。
メーカー側も最近出荷のハスラーには改良ウェザーストリップをつけたりと対応しているようですが、それでもまだ雨漏りすることがあるとかないとか。
まぁ、あったわけですけどもw
もうひとつ。
これは大したことではありませんが、ハンドルのセンターが出ていません。
少し左に傾けた状態で真っ直ぐ進みます。
ハンドルを真っ直ぐにすると右へ進みます。
これは調整ですぐ直るでしょう。
とりあえず、どちらも1ヶ月点検のときに報告し、対応してもらうつもりです。
これから乗っていくと、更に良い部分、悪い部分が出てくると思います。
せっかくですから、そういった諸々も楽しんでいきたいです。
日記 :: comments (6) :: trackbacks (0)
2014.06.24 Tuesday

学名 Solen strictus
和名 マテガイ(馬刀貝)
分類 マテガイ上科 マテガイ科
第9回はマテガイです。
特徴的なその形は、浜でもよく目立ちます。
俺はこのマテガイを掘りたいと常々思っておりまして、小松海岸でも何度か試してみたことがあるのですが、結果は全くの空振りでした。
新しい殻が漂着することから見ても、環境面から考えても、間違いなく生息しているはず……。
うーん、俺の探し方が悪いのでしょうかね。
バター焼きや酒蒸しなど、どのように料理しても美味しい貝です。
パスタに入れたりもします。

マテガイの獲り方。
1、ごく普通の塩を用意します(濃い目の塩水だと尚良いそうです)
2、マテガイの棲んでそうな場所を1〜3cmほど周囲ごと掘り下げます(表面の砂をどける感じ)
3、菱形っぽいカタチをした巣穴があれば、そこに塩を投入します。
4、マテガイが飛び出してきたら、すかさず掴んでゆっくり引き抜きます。
どうでしょう。
文字だけ見ても楽しそうですよね。
皆さんも、マテガイのいそうな場所を見つけたら、是非やってみてください。
そして、もし採取できたら俺にも場所を教えてくださいw
小松海岸の貝図鑑 :: comments (0) :: trackbacks (0)
2014.06.21 Saturday

学名 Anomia chinensis
和名 ナミマガシワ
分類 ウグイスガイ目 ナミマガシワ超科 ナミマガシワ科
第8回はナミマガシワです。
豊富な色彩、およそ貝らしくないセルロイドのような触感、そして透明感ある美しさ。
それら全てが、浜を歩く人々に拾い上げたくなる気持ちを起こさせます。
『波間柏』なんて名前が、また素晴らしく粋ですよね。
小松海岸ではかなりの数が打ち上げられており、集めようと思えば相当の数が集まるでしょう。

さて、このナミマガシワ、他の貝や岩などに付着して生活しています。
打ち上げられているのは殆どが左殻。
右殻はかなり頑丈に岩などにくっついていますので、貝自体が死んでもなかなか剥がれず、あまりお目にかかることがない、というわけです。

1枚目、2枚目の写真にもいくつか混じっていますが、小松海岸では黒いナミマガシワを結構な確率で拾うことができます。
ここまで黒いものは、意外と他県の浜では数が少ないレアものだそうです。
そんなわけで、一部では小松海岸名物 『ブラックナミマガシワ』 なんて呼ばれています。
なぜ黒くなったのか、明確な答えは未だ出ていませんが、砂に埋もれている間に何かしらの成分変化が起こったのではないか、と個人的には考えています。
是非、小松海岸で探してみてください。
小松海岸の貝図鑑 :: comments (0) :: trackbacks (0)
2014.06.18 Wednesday
宍喰の長浜で黒いヤツとひとしきり戯れた後、ようやく今回の目的地である大砂海水浴場へ。時間は既に15時くらい。

人は俺以外、ひとりだけ。
先日の室戸阿南海岸国定公園50周年記念式典の人手が嘘のようです。
まぁ、歩きやすくて何よりですけど。

歩き始めてすぐ、殻頂の残ったウラシマガイが。
ちょっとスレてますが、結構状態は良いです。

今期初のモモタマナ。
やっぱりボチボチと来てるんですね。
去年はこのモモタマナにさえ、殆どお目にかかれませんでした。

おや、このカタチは……シドロガイ、じゃない。
どうやら同じ仲間のフドロガイっぽいです。
殻頂も綺麗に残っていたので、持って帰ろうと手に持った瞬間、凄まじい悪臭が!
残念ですが置いてきましたw

微小貝もこれだけ拾いました。
ここは微小貝好きには天国のような場所ですねー。
念願のウミウサギの仲間も4つゲットすることができました。
現状名前の分からないものなど、同定次第順次ご紹介できたら、と思っております。
問題は同定できるかなんですがw

帰りはいつものをいただいて、午後19時ごろ帰宅。
さて、次に県南へ行くのは一荒れした後かな。
ビーチコーミング :: comments (0) :: trackbacks (0)
2014.06.17 Tuesday
蒲生田の浜でアサガオガイを拾い、ウキウキ気分で更に南下します。メインディッシュである大砂海水浴場は後にとっておき、宍喰の長浜へと向かいました。

この日は薄曇。
風もそこそこあり、あまり暑くないので助かりました。
それでも歩いていると暑いですけどね。
一通り浜を見回ってみたものの、特にこれといったものは無し。
潮が引いていたので、今回は目線を変え、タイドプール観察をしてみました。

タイドプールにはこんな黒いヤツがいました。
クロナマコ? と思ったのですが、検索してみるとどうやらニセクロナマコのようです。

沢山いますw
ニセクロナマコは毒があるらしいですね。
こんなに沢山いるということは、漁師さんも獲らないのでしょう。

結構大きくて、30cm近くあります。
海中から持ち上げると、水とともに肛門から白い粘着質のヒモみたいなものを出しました。
手に絡み付いてなかなか取れませんw
これはキュビエ器官というものだそうで、これによって外敵を追い払うのだそう。
また、クロナマコはこれを出さないとのことです。

クロナマコやニセクロナマコの体表に寄生している貝がいる、というのは知っていましたので、見るナマコ見るナマコとりあえず引っ繰り返して確認しまくったところ、30匹近く調べて3個体の寄生貝を得ることができました。
おそらくはハナゴウナ科のクロナマコヤドリニナだと思います。
爪の先ほどの大きさ、ツヤツヤスベスベ、そして意外にガッチリとナマコの体表に食いついている、という事情もあって、ナマコから取り外すのがわりと大変でしたw
殻高は最大個体で4mmといったところ。
小さいけれど綺麗な貝です。
でも、もう少し大きいのが欲しかったなぁ。
ビーチコーミング :: comments (2) :: trackbacks (0)
2014.06.16 Monday
本日(16日、月曜日)、朝6時頃に家を出て、県南へ行ってきました。今回の狙いは微小貝。
目的地は大砂海水浴場です。

しかし、まずは寄り道から。
蒲生田の浜へ行ってみました。
いやー、久々です。
その久々に訪れた蒲生田の浜で衝撃的な出会いがあるとは、俺は夢にも思っていませんでした。
何ですかね、このミステリー風の書き方w

海草とカキ殻が目立つ中、フィリピンの国民的ビール、サンミゲルが漂着していました。
「imported」とありますね。
まぁ、フィリピンから流れてきたわけではないでしょう。

海草を引っくり返していたら、ヒメハマトビムシとハマダンゴムシに混じってこんな虫が。
クワガタにも匹敵する大顎が特徴のヒョウタンゴミムシです。
洗練された格好良いフォルムですよね。
その後も、大量のヒメハマトビムシの猛攻に耐えつつ、親の仇のように海草を引っくり返します。
ふと、何か青いものがコロッと転がりました。
どうせ磨耗したタカラガイだろう、と思ってチラッと目をやると……。

うおおおお! まさかの! まさかのアサガオガイ!
周りには青いクラゲのクの字もないというのに、こんな場所で初めての青い貝を拾うとは……。
いやはや、ホント分かんないものでございます。
とにかく嬉しい!
来た甲斐がありました。
って、あれ? 大砂海水浴場は?w
ビーチコーミング :: comments (3) :: trackbacks (0)
2014.06.14 Saturday

学名 Erosaria miliaris
和名 ハツユキダカラ
分類 盤足目 タカラガイ超科 タカラガイ科
第7回はハツユキダカラ。
小松海岸で拾えるタカラガイ科の貝としては、メダカラに次いで多い貝です。
浜の真ん中の防波堤から今切川河口まで下を向いて歩けば、少なくとも3つくらいは拾えます。
特徴は茶色っぽい地に雪のような水玉模様と、そこに入る灰褐色のライン。
ビーチコーミングを始めたばかりの頃(といってもまだ数年前)は、ハツユキダカラが拾えたらすごく嬉しかったんですよねー。
そういう意味では思い出深いタカラガイです。
今でも落ちていたら、とりあえず手に取ってみる貝です。

この写真のものは最近拾ったやつですが、結構大ぶりでぷっくりとした良いカタチをしており、ツルピカとは言わないまでもツヤも残っています。
こういう状態の良いものを拾うと、珍しくないと分かっていても何となく嬉しいものですね。
小松海岸の貝図鑑 :: comments (0) :: trackbacks (0)
2014.06.13 Friday

気が付けば、拾ってもう4ヶ月以上経つんですねぇ。
当初は目も塞がり、酷い風邪でどうなることかと思ってましたが……。
結局、我が家の子として迎え入れることになり、懸命の世話によってこんなに元気になりました。
悪戯好きなので大変です。

茶色い涙が出る結膜炎は慢性化してしまっており、獣医さん曰く根治は難しいだろう、とのこと。
マメに拭いてやるしかないようです。
本人が全く気にしてないので、まぁ、いいかな、と。
今は先住のサチ姉さんと同室で、仲良く……はないですが、何とかやっています。
できればもう少し性格的に落ち着いてほしいのですけどねー。
まだ子供なので仕方ないかな、と。
ともあれ、元気に育ってくれれば。
家族 :: comments (0) :: trackbacks (0)