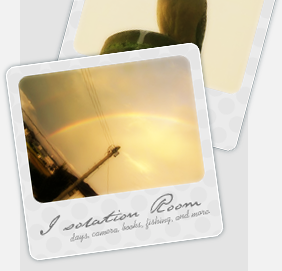2014.07.02 Wednesday

学名 Tegillarca granosa
和名 ハイガイ(灰貝)
分類 フネガイ目 フネガイ科
記念すべき(?)第10回はハイガイです。
貝殻を焼いて石灰を作ったことから、灰の貝でハイガイという名前がつけられています。
ハイガイは亜熱帯性の貝で西日本を中心に分布しており、海水温が高い時代は東北地方まで広く生息していたようです。
縄文時代など古代人の造った貝塚においては構成のメインを占めるほどで、相当の量が食べられていたことが研究で判明しています。
しかし、現代では絶滅の危機にあり、有明海と瀬戸内海の一部で生息を確認できているのみとか。
それだけ環境破壊が進んだ、ということなのでしょうか。
小松海岸では、沢山というほどではありませんが、普通に拾える貝のひとつです。
拾える貝殻はかなり古いもので、少なくとも数百年以上は前のものだと考えられています。
写真のものは見るからに古そうですが、もっと新しそうに見えるハイガイの殻も落ちており、実はもっと最近までそこに存在していたのではないか、と思ってしまいます。

ハイガイは同じ小松海岸で拾えるサルボウとよく似ています。
左がハイガイで、右がサルボウです。
放射肋(殻表面の放射状のスジ)の数がハイガイは16本前後で、サルボウは32本前後となっており、こうやって並べて比較すれば一目瞭然です。
小松海岸の貝図鑑 :: comments (2) :: trackbacks (0)
Comments
初めてコメント差し上げます,天本と申します。
貝殻の写真と解説楽しませてもらっています。ハイガイは国東半島では今でも結構打ち上げられていますね。絶滅のおそれがあると聞いていたのでちょっとびっくりしました。その近辺の貝塚資料を触らせてもらったことがあります。
>天本様
初めまして、コメントありがとうございます。
貝類図鑑は最寄のビーチが海水浴シーズンだったこともあり、しばし停滞しておりましたが、これからまた記事をコンスタントにUPしていけたら、と思っております。
ハイガイ、生きたものは見たことありませんが、国東半島の方ではまだ打ち上げがあるのですねー。
良い環境が残っているのですね。
貝塚において、ハイガイは構成のかなりの割合を占めていることもありますね。
徳島県下の貝塚でも、ハイガイの出土量は貝塚の貝のメインと言っても過言ではないくらい多いようです。
Trackbacks: