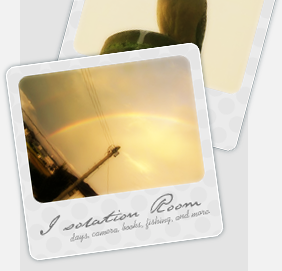2013.12.06 Friday
いつの間にやら、師も走る12月。早いものです。
最近の寒さで少々体調を崩しており、なかなか浜へ赴くことができません。
11月末頃に吉野川のいつもの場所で拾った陶片などの写真を使い、お茶を濁すことにしますw
ただ、この季節は干潮が深夜になる場合が多く、あまり満足にリバーコーミングもできません。
そういう意味でも、早く春になってほしいですね。

いつもの場所でいつもの型紙印判。
しかし、こういう何でもない型紙印判の中に、砥部焼が混ざっているはずなんですよね。
どうにか区別できないものかと思っていますが、これがなかなか……。

鳥の紋が描かれた小皿。
これ、前にも全く同じものを拾ってます。
昭和のものだと思うのですが、こういうの結構好きです。

江戸陶片らしいものたち。
左上と下は随分と黒っぽい呉須で描かれています。
黒いものは質が悪いらしいですね。

最も困る土もの。
左は内側に青磁的な釉薬のかかったもの。
全体に貫入が入っています。
右は染付けがあります。
どちらも(少なくとも右は)それなりに古いものではないかと考えています。

土器的なもの。
以前にもご紹介した、一番下の赤茶色で細かい溝の入ったタイプの土器片。
実はこれ、古い瓦か何かの破片であって、土器ではないんじゃないか、と疑ってたんですよね。
それで、ちゃんと「これは土器だ」といえるようなサンプルが見つかればなー、と目を小松海岸を歩くときと同じ、土器モード(?)にして歩いていたら、何のことはない、ちゃんとそれっぽいものが拾えましたw
特に上段左のものは口の部分ですから、紛うことなき土器片と言っていいと思います。
(タコツボだったりして)
上段右は小さな欠片なんですが、どうも須恵器質な感じです。
中段のものは、溝の目が粗く、もしかしたら古い擂鉢かも?
もう少しサンプルを拾っておいて、今度の観察会で陶片顧問N氏に見ていただこうと思います。
リバーコーミング :: comments (2) :: trackbacks (0)
Comments
なかなか多彩な陶片が上がってますね。
型紙印判の湯呑み?は、なんだか可愛らしい感じですね。
この柄の組み合わせのは、こちらでは見たことがないような…。
江戸陶片も小さいですが、雰囲気があります。
上左のタイプはこちらでもよく見かけます。
それだけ雑器だったのでしょうけれど、好きな雰囲気です。
下の写真2枚のようなものは難しいですね。
このあたりまでわかるようになると楽しみも広がるのでしょうけれど
ちょっと難易度が高すぎます(笑)
>尚様
色々な時代の様々な陶片が出るので大変面白いのですが、逆に混ざりすぎていて困りますw
一番上の型紙印判ですが、サイズ的には湯呑と茶碗の間くらいの大きさです。
向付といったところでしょうか。
俺としても、「ちょっと珍しい柄の組み合わせだな」と思って拾ったものなんです。
雑器とはいえ、やはり江戸陶片は趣がありますよねー。
黒っぽい呉須のものは、骨董的には価値が低いそうなのですが、個人的に渋い感じがして好みです。
左上のタイプは、吉野川のいつもの場所だけでなく、旧吉野川でも拾っています。
やはり、大量生産品なのでしょう。
土ものは本当に分かりません……w
勉強になるかと思い、器の本をいくつか買ってみたのですが、なかなか厳しそうです。
実際に沢山の焼物を見て、じっくり目を養うしかないのでしょうね。
陶片拾いをもっと楽しむために、頑張ってみたいと思いますw
Trackbacks: