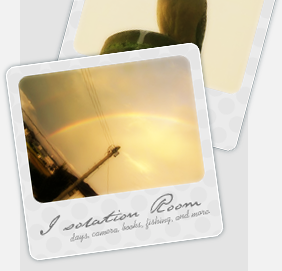- 今昔妖怪図鑑 河童 [2] (04/17)
- 今昔妖怪図鑑 河童 [1] (04/15)
- 風呂好きの叫び (04/11)
2005.04.15 Friday
最近、民俗学関連の記事が少ないので、俺が片手間に調べている妖怪に関することを、これまた片手間に書いていこう、という趣旨の元、これを今昔妖怪図鑑と銘打って記事にしていこうと思います。第一回は河童です。
説明するまでもないくらい、妖怪の中でもメジャーで人気のあるヤツです。
メジャーなだけに全国各地、至る所に伝承が残っており、その眷属の数たるや、星の数ほどではないか、とさえ言われている……かどうかは知りませんが、そんな風に思っても不思議ではないほど、各地に広く分布しています。
当然、呼び名だけでもゴマンとありまして、川太郎、ガタロウ、川原坊主、ホンコウ、水虎、メドチ、ドチガメ、ケンムン等々、まさに枚挙に暇がない、といった感じです。
「所変われば品変わる」といいますように、呼び名だけではなく、その見た目も地方によって全く違ったりします。
河童のイメージといえば、黄桜のCMで見たことがある方もいらっしゃるでしょうが、頭に皿、背中には亀のような甲羅、というものが一般的ですね。
しかし、どうみても猿にしか見えないものもあれば、四速歩行の獣的なもの、更には怪獣そのものといったような出で立ちのものまであり、なかなかレパートリーの多い(?)ヤツらなのです。
さて、今回は最もオーソドックスな、頭に皿、背中に甲羅の河童の話をしましょう。
特徴は先に挙げた二つに加え、以下のようなものもあります。
・手には水かき
・キュウリが好物
・怪力の持ち主であり、相撲が好き
・牛や馬を池や川に引きずり込む
・人間の尻子玉を抜き取る
・左右の腕が体内で繋がっており、右の腕を伸ばすと左の腕が引っ込む
これだけ特徴の多い妖怪というのは、なかなか他に見当たりません。
では、どうして河童はここまで事細かに、特徴やイメージが作られたのでしょうか。
当時の人々にとって川や池というのは、生活の場であると同時に境界であり、神の在る場所でした。
そして、日本書紀に見られる “ミヅチ” が、地方によっては河童の呼び名として使われていることからもわかるように、河童は水神としての役割を与えられた妖怪です。
生活に密着した神霊であるからこそ、人々は河童に色々な特徴を付与し、信仰と畏れの対象としたのではないでしょうか。
現代のように水道を捻れば水が出る、といった生活をしていては、河童の出る幕などなかったでしょうね。
とりあえず今日はこれくらいにして、続きはまた明日。
次回は俺の体験談や、祖父のしてくれた昔話、そして河童の系統について書きます。
民俗学 :: comments (3) :: trackbacks (0)
Comments
少し話がずれますが、逆に水のない過酷な土地(砂漠など)では唯一神信仰が多く見られます。
こういった違いも民俗学的に面白いなあと思います。
今気づいたけどレスの文章が飛んでました。
これじゃどういう意図でレスしたかわからないね。ごめんなさい=■●
要するに何が言いたかったかと言うと水や森といった自然溢れる国は多神教であることが多いので、四季が豊かな日本に河童の種類が沢山あるのも納得ですね〜ってことでした(●´ω`●)ゞエヘヘ
例を挙げるならば、日本は四季のある豊かな風土だからこそ、八百万の神々が生まれたのでしょう。
自然が豊かであるということは、人間にとって恵まれているということ。
そして、自分たちに恵みをもたらしてくれるものに神を見ることは、逆に自分たちを脅かすものに神を見ることにも繋がります。
日本で言えば、それが鬼であったり妖怪であったりするわけです。
今回の河童は水神の零落した姿と言われていますが、その水神にしても色々といるわけで、なかなかややこしいですな……(笑)
Trackbacks: