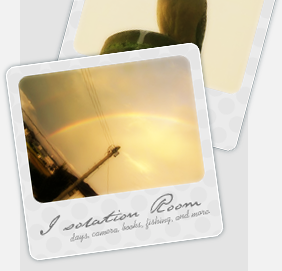- 陶芸やってみたい! その1 (10/09)
- 干潟産陶片など (10/09)
- 長国の埋蔵文化財 2 (10/03)
2014.10.09 Thursday
ここしばらく忙しく、なかなか海にも行けずにいます。気付けば10月も中旬になろうとしているんですよね。
早いものです。
そういえば、猛烈な強さの台風19号が接近しています。
週明けあたりは気をつけないといけません。

さて、しばらく前に古川の渡し跡で拾ってきた陶片です。
左上はかなり大きな染付け鉢。
漆継ぎでしょうか。
一度割れたものを直して使っていたようです。
右上は微塵唐草の皿で、型紙摺りの後に濃みを入れています。
下段左は縁起物(福の字、打ち出の小槌)の描かれた型紙摺りの椀。
下段中央は花唐草文の……椀の蓋でしょうか。
見込みに蛇の目釉剥ぎがあります。
下段右は牡丹っぽい花の湯呑か何か。

左の大きいのは、大谷焼の瓶です。
上段左と上段中央は灯明具の一部だと思います。
時代は展示品と同じだと考えると、19世紀〜幕末ということになります。
上段右は大谷焼の徳利の底ではないかと思います。
下段左は見込みに鳥文の描かれた染付け椀。
下段中央は蛸唐草文の御神酒徳利の一部でしょう。
下段右は染付けの小さな鉢、もしくは手塩皿的なもの?
どれも18世紀後期以降のものだと思います。

大砂海水浴場のハケで拾った御神酒徳利は、クリーニングが終了しました。
何とかコンクリ塊を除去することができましたが、コンクリの付着していたあとはザラザラです。
まぁ、仕方ありませんね。
リバーコーミング&陶片 :: comments (2) :: trackbacks (0)
Comments
上の写真の大きな陶片、時代は少し若そうな感じですが
金継ぎして使っているなんて、大切にされていたんですね〜。
2枚目の写真上段の大谷焼とか、この手のタイプは苦手です。
勉強不足でぜんぜん判別がつけられません(苦笑)
例の御神酒徳利も綺麗になりましたね。素敵な色合いです。
>尚様
今しがた、継ぎ接ぎ陶片をしげしげと見ていたのですが、これは漆継ぎではなく、焼き継ぎなのかもしれません。
うーん、見分け方がイマイチわからず、です。
とはいえ、継いでまで使っていたのですから、大事だったことは確かなのでしょう。
大谷焼の類は、今回県立博物館での展示準備作業において、学芸員さんや館長さんに同定していただいたおかげで、ほんの少しではありますが、目を養うことができましたw
それにやはり産地ということもあり、大谷焼の陶片はかなり目に付きます。
御神酒徳利、クリーニングが大変でした。
小さなタガネとハンマーでコチコチと削る作業で、随分と肩が凝りました。
これじゃ化石の発掘なんてできないでしょうねぇw
Trackbacks: