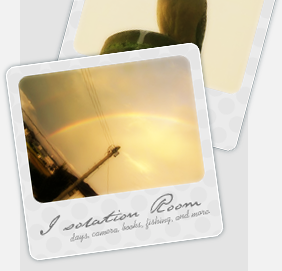- 正貴寺跡現地説明会 (04/01)
- 大谷焼の里ちょい歩き (03/07)
- 宇志比古神社参道の陶片 (02/24)
2015.03.07 Saturday
さて、宇志比古神社参道で多くの陶片を見つけたわけですが、この近辺は大谷焼の窯元が集まった、まさに大谷焼の里と言える場所です。落ちていた陶片も7割くらいは大谷焼関連だったような気がします。
そんなわけで、別の日に東林院駐車場に車を停め、周囲を散策してみました。

宇志比古神社から北東へ歩いていくと、石垣の代わりに窯道具が積まれている場所が。
『阿波の焼物』によれば、この辺は廃窯跡が多いらしいです。

何となく撮影した写真なんですが、この場所こそ1780年からたったの3年間、徳島で染付け磁器が焼かれた藩窯の跡だそうです。
帰宅して色々調べてから気付きましたw
笹やら何やらが茂っており、中は完全に藪。
一応、鳴門市史跡らしいので、せめて見学できる程度に整備してほしいですねぇ……。

藩窯跡を東に見ながら、山に続く坂道をほんの少し登ると、足元に大谷焼の破片や窯道具が散らばった場所に出ます。

崖には窯道具や大谷焼の破片が埋まっています。
上は藩窯のはず。

少し引き返して、途中にあった分かれ道を右に曲がります。
壷のようなものが石垣の代わりに積まれています。

中にはこのように店名の書かれたものも。

ずんずん歩いていきます。
草に隠れていますが、延々と壷が積まれています。

こんな感じです。
一体何個あるんでしょうね。
というか、よくこれだけバランス良く積んだもんです。

広場の向こうに何か……と思ったら、どうやら登り窯のようです。

これは大西陶器が所有している登り窯ですね。
今も使ってるのかな?

今回歩いたのはこのルート。
往復しても1kmちょっと程度です。
良い散歩になりました。
できればいつか、藩窯跡に潜入してみたいですw
リバーコーミング&陶片&ビン :: comments (4) :: trackbacks (0)
Comments
いや〜ここ、めちゃくちゃ楽しそうですね!
廃窯道具利用の石垣とか、積み上げた壺とか、雰囲気ありますね〜。
こういうの見たら、写真撮りまくりそうです。
このような場所はこちらにはないので、とても興味深いです。
>尚様
楽しいですよー!
歩いているだけでワクワクする場所です!
大谷焼自体は正直、大した知名度もありませんし、作っているモノも日常雑器が殆どで、特徴があるといえば寝ロクロという二人がかりで巨大ロクロを使って作る睡蓮鉢や大甕くらいのものです。
商品そのものだけではなく、廃窯跡や登り窯跡などを安全に観光できる『歴史ある焼き物の町』という方向で売り出してもいいんじゃないかなぁ、と思います。
廃窯跡は殆ど山や藪の中なので、整備してくれれば見学しやすいですしねー。
難しいところですね。
観光のために整備すると、この雰囲気が台無しになりそう…。
行政とかには、こういう寂れた雰囲気が良いというのが理解できない人が多いですからね。
お客さんを迎えるんだから、事故が起きたら困るから…と、
変にきれいにして、余計なものまで作りそうですから(苦笑)
登り窯の手前、野面積みの石垣も風情がありますね!
>尚様
なるほど、ごもっともです。
何だかこう、行政はやりすぎた整備をしそうというか、余計なことをしそうというか……。
そういうのが容易に想像できますよねぇ。
そう考えると、あまり手が入らないままの、知ってる人だけが知っている場所の方がいいのかもしれません。
田舎なもので、どうしてもすぐ観光という方向を考えてしまいますが、観光地化することで失われてしまうもの、というのは確実に存在すると思います。
野面積みの石垣は、主に青石(緑泥片岩)で出来ています。
当時のものなのかどうかはちょっと分からないですが、趣があっていいですよねー!
Trackbacks: