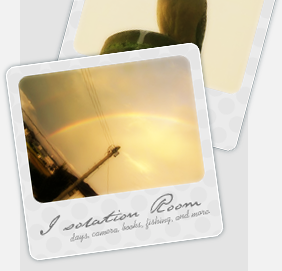2015.01.16 Friday
ここ最近、また風邪ひいてる俺です。おかげで海にも川にも行けてません。
ほんと情けない限り……。
というわけで、風邪をひく前に行った古川の渡しで拾ったものをご紹介。
今回、数は少ないのですが、ちょっと面白いモノが。

まずは碗二種。
左は広東高台の碗。
19世紀初期頃のものかな、と。
右は松葉文のくらわんか碗。
見込みは蛇の目に釉剥ぎされています。
18世紀後期くらいでしょうか。

次はこちら、瀬戸っぽい肌の陶片二種。
こういう肌の陶片はボチボチ見ますが、左の皿のように大きな破片で出ることは非常に稀です。
右の二つは元々ひとつだったものです。
織部っぽい緑の釉がかかっています。
どちらも時代不明。
……19世紀くらいじゃないかなぁ、と予想。

冒頭で書いた面白いモノというのがコレです。
蛇の目釉剥ぎを失敗したくらわんか系豆皿、みたいな感じでしょうかw

ご覧のように、二枚が完全に重なってくっついちゃってます。
引っ張ってもビクともしません。
これ、干潟の土手に高台部分だけ出して埋まっているのを見つけ、素手で苦労して掘り出したのですが、二枚重なってるのが分かったときに、「お、もしかして灯明皿?」なんて期待したものの、実際は不良品というオチでしたw
しかし、こういう明らかな不良品は窯場ですぐに棄てられそうなものですけどねぇ。
リバーコーミング&陶片&ビン :: comments (2) :: trackbacks (0)
Comments
なかなか時代的におもしろいものが出ますね〜。
2枚目の写真左にある皿のようなものは、こちらでは見かけません。
最後の重なった豆皿もとっても興味深いです。
普通に考えれば、ご推察の通り窯で焼きに失敗したものに見えますが
あるいは焼き継ぎ的なことをしようとして失敗したとか…?(笑)
>尚様
18世紀初期から中期までが限界で、それより古いものは出てこないんですよね。
古唐津とか出てくれたら面白いのですがw
写真2枚目のような陶片……瀬戸焼系なのか、京焼系なのか、はたまたそれ以外なのか、浅学な俺にはわからないのですが、そちらでは見られないということから関西以西に多く流通したものなのかもしれません。
豆皿ですが、二枚重なった上側にもくっついていた跡がありますので、もしかしたら沢山重なったまま流通させ、必要なものだけ剥がして使ってたのでは!? なんてことも考えたりしましたw
もしくは、一定量混じる不良品を、この渡し場で選別して棄てていたのかも……。
やたら想像は膨らみますが、謎は解けませんw
でも、こういう背景を感じられるのも、陶片の面白いところですよね!
Trackbacks: